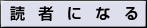いま、ふたたびの…新薬師寺
テーマ:たび
2011/08/02 14:17
娘も受験生になり、冬の京都を最後にしばらく旅行は休みにしよう、そう心に決めたし娘にも言い聞かせたわたしでしたが、きっかけはJR東海の「うまし うるわし 奈良」のテレビCMでした。
そこで新薬師寺が取り上げられ、それを見た娘が「いいなぁ、行きたいなぁ」と思わずつぶやいた時、わたしの中にもわき上がる懐かしいものがあり、ぜひ連れて行ってやりたいと思ったのでした。
(調べたら動画が見つかりました。こちらです)
わたしが新薬師寺の宿坊にお世話になったのは、調べてみると何と今から33年も前のこと。
1週間近く泊めていただき、そこを拠点にそれこそ奈良中を歩き回ったのでした。
大好きだった興福寺国宝館には毎日のように通いましたが、それ以上に朝夕通ったのは勿論この新薬師寺本堂でした。
本尊である薬師如来様と十二神将を、宿泊客は拝観時間に関係なく早朝夕刻にお詣りする事が出来たのでした。
仏像が好きだという娘にもぜひその経験をさせてやりたいと調べたのですが、残念なことに宿坊は6年前にやめられたとのこと。まあ、そのお陰で今回の宿泊先「ゲストハウス奈良バックパッカーズ」と出会えたのですが、それはまた後ほど…。
今回の旅行の最終日になりましたが、ようやく新薬師寺を訪ねる事が出来ました。

毎日歩いて通った高畑の路は今もさほど変わっていない気がしました。
そして、もちろん変わる筈のない山門と本堂、築地塀。



南門をくぐり、本堂手前左手に建つ地蔵堂を巡れば、そこに観音堂(香薬師堂とも)へと通じる小さな門があります。

石張りの路を辿って池を渡り、正面の観音堂から右手を見たところにかつて宿坊であった庫裏が今もかつての佇まいのままに残っていました。

かつてこの宿坊で相部屋となった方のうち、栃木県栃木市の高校で社会科の教諭をされていた方と福井県小浜市の郷土史家の方には特に親しくして頂き、旅の後もしばらくの間手紙での交流をさせて頂いたものでした。
観音堂から庫裏にかけての庭は織田有楽斉の手によるものであるとか。




これらの庭を毎日眺めつつ、同宿の大先輩方に奈良の歴史や史跡の話を伺い、

この玄関を抜けて、

この門をくぐって奈良の町に出掛けて行った頃のことを思い出したのでした。
いずれにせよ、この父の思い出の寺を娘も気に入ってくれた様子だったのはとても幸いなことでした。

そこで新薬師寺が取り上げられ、それを見た娘が「いいなぁ、行きたいなぁ」と思わずつぶやいた時、わたしの中にもわき上がる懐かしいものがあり、ぜひ連れて行ってやりたいと思ったのでした。
(調べたら動画が見つかりました。こちらです)
わたしが新薬師寺の宿坊にお世話になったのは、調べてみると何と今から33年も前のこと。
1週間近く泊めていただき、そこを拠点にそれこそ奈良中を歩き回ったのでした。
大好きだった興福寺国宝館には毎日のように通いましたが、それ以上に朝夕通ったのは勿論この新薬師寺本堂でした。
本尊である薬師如来様と十二神将を、宿泊客は拝観時間に関係なく早朝夕刻にお詣りする事が出来たのでした。
仏像が好きだという娘にもぜひその経験をさせてやりたいと調べたのですが、残念なことに宿坊は6年前にやめられたとのこと。まあ、そのお陰で今回の宿泊先「ゲストハウス奈良バックパッカーズ」と出会えたのですが、それはまた後ほど…。
今回の旅行の最終日になりましたが、ようやく新薬師寺を訪ねる事が出来ました。

毎日歩いて通った高畑の路は今もさほど変わっていない気がしました。
そして、もちろん変わる筈のない山門と本堂、築地塀。



南門をくぐり、本堂手前左手に建つ地蔵堂を巡れば、そこに観音堂(香薬師堂とも)へと通じる小さな門があります。

石張りの路を辿って池を渡り、正面の観音堂から右手を見たところにかつて宿坊であった庫裏が今もかつての佇まいのままに残っていました。

かつてこの宿坊で相部屋となった方のうち、栃木県栃木市の高校で社会科の教諭をされていた方と福井県小浜市の郷土史家の方には特に親しくして頂き、旅の後もしばらくの間手紙での交流をさせて頂いたものでした。
観音堂から庫裏にかけての庭は織田有楽斉の手によるものであるとか。




これらの庭を毎日眺めつつ、同宿の大先輩方に奈良の歴史や史跡の話を伺い、

この玄関を抜けて、

この門をくぐって奈良の町に出掛けて行った頃のことを思い出したのでした。
いずれにせよ、この父の思い出の寺を娘も気に入ってくれた様子だったのはとても幸いなことでした。

奈良きたまち界隈 依水園と吉城園
テーマ:ガーデン
2011/08/01 07:40
奈良5日目。
宿の周辺をめぐって東大寺の伽藍と国立博物館、それにふたつの庭園を訪ねました。
思えば東大寺も大仏殿に関して言うと中学校の修学旅行以来…
二月堂や三月堂、戒壇堂に立ち寄ることはあっても大仏様にはすっかりご無沙汰しておりました。
久々にお目にかかって、すこし感動。
三月堂は現在解体修理と調査のために拝観停止中で、かろうじて何体かの仏像を拝めるだけでした。
堂内狭しと居並ぶ仏たちの姿が好きだっただけにとても残念。
でも、帝釈天や弁財天、日光・月光菩薩といった天平仏を間近で拝めるのはなかなか得難い経験と思いました。
この日は天候に恵まれた(幸か不幸か?)奈良旅行の中でも特によい天気で、つまりめちゃくちゃ暑く、本当は国立博物館で開催されている「天竺へ 三蔵法師3万キロの旅」の世界に浸り切りたかったのですが、でもこれが最後のチャンスという訳なので、宿からすぐそばに並ぶふたつの庭園を訪ねました。

依水園は江戸期、明治期と別々の時代に作られたふたつの庭園と寧楽美術館、食事処「三秀亭」から構成されていて、東大寺の戒壇堂近くに吉城(よしき)川を挟んで吉城園庭園と隣り合ってありました。

まずこれが江戸期に作られた庭園。
江戸初期の延宝年間に建てられた三秀亭を中心にした、石組と池とがとても落ち着いたお庭です。

そしてその奥にある明治32年、裏千家十二世又妙斉が作り上げたという庭園。
背景に東大寺伊大仏殿と左から若草、春日、三笠の三山を取り入れたゆったりとおおらかな庭園でした。
見どころは何といっても吉城川の水をふんだんに取り入れた動きのある水の演出。そして、延段、階段、飛び石とさまざまに表情を変えてみせる石の演出だと思います。




明治期の庭園らしく、伝統的な美しさの中にモダンな意匠が凝らされてとても個性的です。

昨夜の雨で少し息を吹き返したという苔の庭も明るく伸び伸びとした印象ですね。


塀ひとつを隔てた外はとても暑いのですが、木陰と水の流れがとても涼しく、生き返った心地でした。


そしてこちらが吉城園。

古くからあった場所ですが庭園として整備されたのは大正のようです。
個人の所有から今は県の管理に移っています。

池をめぐる手前の庭の奥に、


茶室から望む苔の庭園が広がります。
全体に起伏に富んでいるため、その地形を生かした昇降に趣があります。
依水園が動の庭とするなら、こちらは静のお庭。


しっとりとした落ち着きの中に軽妙なリズムを感じさせてくれました。

奈良最終日の今日は、「いま、ふたたびの奈良へ」。
この奈良旅行のきっかけとなった懐かしい新薬師寺を高畑に訪ねることにします。
宿の周辺をめぐって東大寺の伽藍と国立博物館、それにふたつの庭園を訪ねました。
思えば東大寺も大仏殿に関して言うと中学校の修学旅行以来…
二月堂や三月堂、戒壇堂に立ち寄ることはあっても大仏様にはすっかりご無沙汰しておりました。
久々にお目にかかって、すこし感動。
三月堂は現在解体修理と調査のために拝観停止中で、かろうじて何体かの仏像を拝めるだけでした。
堂内狭しと居並ぶ仏たちの姿が好きだっただけにとても残念。
でも、帝釈天や弁財天、日光・月光菩薩といった天平仏を間近で拝めるのはなかなか得難い経験と思いました。
この日は天候に恵まれた(幸か不幸か?)奈良旅行の中でも特によい天気で、つまりめちゃくちゃ暑く、本当は国立博物館で開催されている「天竺へ 三蔵法師3万キロの旅」の世界に浸り切りたかったのですが、でもこれが最後のチャンスという訳なので、宿からすぐそばに並ぶふたつの庭園を訪ねました。

依水園は江戸期、明治期と別々の時代に作られたふたつの庭園と寧楽美術館、食事処「三秀亭」から構成されていて、東大寺の戒壇堂近くに吉城(よしき)川を挟んで吉城園庭園と隣り合ってありました。

まずこれが江戸期に作られた庭園。
江戸初期の延宝年間に建てられた三秀亭を中心にした、石組と池とがとても落ち着いたお庭です。

そしてその奥にある明治32年、裏千家十二世又妙斉が作り上げたという庭園。
背景に東大寺伊大仏殿と左から若草、春日、三笠の三山を取り入れたゆったりとおおらかな庭園でした。
見どころは何といっても吉城川の水をふんだんに取り入れた動きのある水の演出。そして、延段、階段、飛び石とさまざまに表情を変えてみせる石の演出だと思います。




明治期の庭園らしく、伝統的な美しさの中にモダンな意匠が凝らされてとても個性的です。

昨夜の雨で少し息を吹き返したという苔の庭も明るく伸び伸びとした印象ですね。


塀ひとつを隔てた外はとても暑いのですが、木陰と水の流れがとても涼しく、生き返った心地でした。


そしてこちらが吉城園。

古くからあった場所ですが庭園として整備されたのは大正のようです。
個人の所有から今は県の管理に移っています。

池をめぐる手前の庭の奥に、


茶室から望む苔の庭園が広がります。
全体に起伏に富んでいるため、その地形を生かした昇降に趣があります。
依水園が動の庭とするなら、こちらは静のお庭。


しっとりとした落ち着きの中に軽妙なリズムを感じさせてくれました。

奈良最終日の今日は、「いま、ふたたびの奈良へ」。
この奈良旅行のきっかけとなった懐かしい新薬師寺を高畑に訪ねることにします。