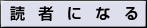地震のあと02
テーマ:思い
2011/03/16 06:11
亡くなった家内は生前、行列を作ってまでものを買うのを極端に嫌った。
並ばないと食べ物が手に入らないなら、飢えて死んだ方がマシとさえ言っていた。
独特の価値観であり美意識であって、手放しで誉められないのだけれど、わたしは割と共感していた。
現在中学2年になるひとり娘も、別に母親から訓戒を受けた訳でもないのにまったく同じ美意識を持っている。人を押しのけてまで生きることに執着することを、どうやら醜いことだと思っているらしい。生への執着が希薄なのは、わたしの教育が間違っていたのだろうか。それとも母親から受け継いだDNAのなせる業か…。
いずれにしても、災害時には絶対生き残れないタイプだろう。生き残る生き残れないはともかくとしても、他者だけでなく自分の命をもっと大切に思えるよう導くのが、わたしの役割だろうと考えている。
ガソリンスタンドからガソリンが消えた。
風評やパニック心理のせいもあるのだろうが、このところずっとスタンドには長蛇の列が出来、そうしたスタンドも次々と休業し、昨日あたりは現場に向かう1時間半ほどの間に1軒も開いていなかった。
妻や娘同様に行列に並ぶことが好きでないわたしのクルマに、残ったガソリンはごく僅かなものとなってしまった。
まあ良い。
昨日無事にコンクリートの打設を終え、これで万が一わたしの身に何があってもお客さんに掛かる迷惑は最小限のものになったと思う。型枠の脱型と現場の仕上げは行列なしで給油出来るようになってからで良いだろう。
別にわたしが買い損なったガソリンが被災地に廻される訳ではないし、わが家が買い出しを自粛することにした乾電池とか即席麺とか灯油とかが、その分被災者の皆さんの手元に届く訳ではないのだけど…
そうそう。単に美意識だとしたらまったくの自己満足に老祖母と娘を巻き込んでいるに過ぎない。まあ、娘は賛同してくれるだろうけれど。
そんな訳で残念なことにわたしの経済活動は、ここではかなくも中止となる。
今後は会社や近場で出来る仕事に専念したい。
幸いなことに近場でもわたしを必要としてくれている人が居てくれているので…
サンフランシスコに住む古い友人が昨日教えてくれたビデオがある。
「3/14(第4回)福島原発に関するCNIC記者会見 中継」と題された東芝の元原子炉格納容器設計者である後藤政志さんの会見の様子である。
1時間以上に及ぶ長くて、しかもたどたどしい会見だが、その内容には驚かされたし深い感銘を受けた。
ぜひ観ていただきたい。
http://www.ustream.tv/recorded/13320522
わたしの比では全くないが、こうした危機的状況のときこそ、しっかりとした信念と価値観、それに時として美意識をもって事に臨むべきであることを強く示唆してくれている。
並ばないと食べ物が手に入らないなら、飢えて死んだ方がマシとさえ言っていた。
独特の価値観であり美意識であって、手放しで誉められないのだけれど、わたしは割と共感していた。
現在中学2年になるひとり娘も、別に母親から訓戒を受けた訳でもないのにまったく同じ美意識を持っている。人を押しのけてまで生きることに執着することを、どうやら醜いことだと思っているらしい。生への執着が希薄なのは、わたしの教育が間違っていたのだろうか。それとも母親から受け継いだDNAのなせる業か…。
いずれにしても、災害時には絶対生き残れないタイプだろう。生き残る生き残れないはともかくとしても、他者だけでなく自分の命をもっと大切に思えるよう導くのが、わたしの役割だろうと考えている。
ガソリンスタンドからガソリンが消えた。
風評やパニック心理のせいもあるのだろうが、このところずっとスタンドには長蛇の列が出来、そうしたスタンドも次々と休業し、昨日あたりは現場に向かう1時間半ほどの間に1軒も開いていなかった。
妻や娘同様に行列に並ぶことが好きでないわたしのクルマに、残ったガソリンはごく僅かなものとなってしまった。
まあ良い。
昨日無事にコンクリートの打設を終え、これで万が一わたしの身に何があってもお客さんに掛かる迷惑は最小限のものになったと思う。型枠の脱型と現場の仕上げは行列なしで給油出来るようになってからで良いだろう。
別にわたしが買い損なったガソリンが被災地に廻される訳ではないし、わが家が買い出しを自粛することにした乾電池とか即席麺とか灯油とかが、その分被災者の皆さんの手元に届く訳ではないのだけど…
そうそう。単に美意識だとしたらまったくの自己満足に老祖母と娘を巻き込んでいるに過ぎない。まあ、娘は賛同してくれるだろうけれど。
そんな訳で残念なことにわたしの経済活動は、ここではかなくも中止となる。
今後は会社や近場で出来る仕事に専念したい。
幸いなことに近場でもわたしを必要としてくれている人が居てくれているので…
サンフランシスコに住む古い友人が昨日教えてくれたビデオがある。
「3/14(第4回)福島原発に関するCNIC記者会見 中継」と題された東芝の元原子炉格納容器設計者である後藤政志さんの会見の様子である。
1時間以上に及ぶ長くて、しかもたどたどしい会見だが、その内容には驚かされたし深い感銘を受けた。
ぜひ観ていただきたい。
http://www.ustream.tv/recorded/13320522
わたしの比では全くないが、こうした危機的状況のときこそ、しっかりとした信念と価値観、それに時として美意識をもって事に臨むべきであることを強く示唆してくれている。
地震のあと
テーマ:思い
2011/03/13 23:08
地震から一日半が経過して、ようやく散乱した部屋の片づけをした。
当日は停電で手の付けようがなかったし、昨夜は電気が戻っていたけれど、東北地方の惨状を知って手を付ける気力を失った。
地震発生時は現場にいて、あまりの揺れの激しさに立っているのさえおぼつかなかった。
まず頻発していた三陸沖が震源かとも思ったが、これがもしそうならあちらはいったいどういうことになっているのかと恐ろしくなった。それくらいの揺れだったし、激しい余震が何度もきた。
当然の事ながら電話は通じず、ラジオの放送だけでは被害の様子が一向につかめず、とりあえずやりかけた作業を終え(モルタルはすでに液状化を起こしていたので全て回収して練り直して)、施主さんのお宅の中の余震で倒れたら困る重量物を安全なところに移して、停電で信号機の止まってしまった街を帰路についた。
その間も情報を集めようとするのだが、被災地の惨状を知ることはその時点ではまだ出来なかった。
阪神淡路の被災地を思った。
おそらくあれよりもひどいに違いないとは想像出来た。
途中、信号が復旧していたので少し期待していたのだが、案の定わが家のある地区は真っ暗だった。
プロパンガスが無事だったので、鍋でご飯を炊きロウソクの灯りで夕食を摂った。
明日に備えて出掛けたスーパーから、すでにパンはごっそりと消えていた。
幸い電気なしで使える石油ストーブが1基あったのでそれ一台で家族4人暖をとって、ラジオだけを聞きながら長い夜を過ごした。
夜中にパソコンが息を吹き返す音で電気の復旧を知った。
その時間まで復旧作業に追われ続けてこれからもそれを繰り返すのであろう電力会社のみなさんのご苦労を思った。頭が下がる。
これから長い苦労が始まる。
被災者の救出、避難所の運営、ライフラインの復旧、仮設住宅の建設、瓦礫の片付け、町の再建…
阪神淡路を思い、中越地震を思って、またあの途方もなく長いプロセスが繰り返されるのかと暗澹たる気持ちになる。
が、そんなものではないということを昨夜のテレビ中継で思い知った。
阪神淡路については被災地で働いたから分かるが、あの時は活断層に沿って被害が集中して無事なところとそうでないところとが比較的はっきりとしていた。つまり、その気になれば被災地に直接アプローチ出来た。また、被害の軽い人が重い人の支援に廻ることも出来た。
でも今回は町がごっそり全部壊されている。ほとんどの人が同等の被害を受け、持てるものの全てを失っている。
だから、まったく外部からの支援を待つしかない。
被災者の救出以前に、まず安否確認だけでもまだまだ時間がかかるだろう。
さらには福島第一原発のトラブルもある。
いったい誰がどうやったらそれらの町を元に戻せるのだろうかと、そんなことを思いながらテレビの画面を見るのが辛かった。
その惨状を伝えるために撮られたヘリからの映像が、その騒音で救出作業や避難所生活にとんでもない障害と負担を与えていることを思いつつ。
いつもそうだが、いま自分に何が出来るのかと思う。
わたしはこれまでの経験で、それが、
自分の持ち場で自分に出来る経済活動をしっかり行うことだと知っている。
自分が本来抱えている責任を投げ出して、現地に赴いてボランティアに身を投じるのではないことを知っている。
しっかりと仕事をしてしっかりと収入を得て、それを支援に回せるのなら、それが一番良いことだと知っている。
明日からは計画停電がスタートする。
うちの町は初日の最初の時間帯から停電となる。そして、夕方から夜の8時までの一日2回らしい。
それがどれほどの不便だろうか?
少なくとも被災地の状況を思えば…
う~ん。
今年最初の生コン打設がようやく出来ると思っていたが、きっとプラントは操業停止に近い状態になるのだろうな。
わたしのデスクトップPCもしばらくは操業停止…かもしれない。
ブログも再びお休みとなりそうだけど、その間、誰にも恥じることのない仕事に務めたい。
こんな長々と書き連ねなければ、被災地のみなさんへの思いを表すことの出来ない自分だが、それでもまだまだ言葉が足りない気がする。
足らないあとの分は、ただひたすら、祈ろうと思う。
当日は停電で手の付けようがなかったし、昨夜は電気が戻っていたけれど、東北地方の惨状を知って手を付ける気力を失った。
地震発生時は現場にいて、あまりの揺れの激しさに立っているのさえおぼつかなかった。
まず頻発していた三陸沖が震源かとも思ったが、これがもしそうならあちらはいったいどういうことになっているのかと恐ろしくなった。それくらいの揺れだったし、激しい余震が何度もきた。
当然の事ながら電話は通じず、ラジオの放送だけでは被害の様子が一向につかめず、とりあえずやりかけた作業を終え(モルタルはすでに液状化を起こしていたので全て回収して練り直して)、施主さんのお宅の中の余震で倒れたら困る重量物を安全なところに移して、停電で信号機の止まってしまった街を帰路についた。
その間も情報を集めようとするのだが、被災地の惨状を知ることはその時点ではまだ出来なかった。
阪神淡路の被災地を思った。
おそらくあれよりもひどいに違いないとは想像出来た。
途中、信号が復旧していたので少し期待していたのだが、案の定わが家のある地区は真っ暗だった。
プロパンガスが無事だったので、鍋でご飯を炊きロウソクの灯りで夕食を摂った。
明日に備えて出掛けたスーパーから、すでにパンはごっそりと消えていた。
幸い電気なしで使える石油ストーブが1基あったのでそれ一台で家族4人暖をとって、ラジオだけを聞きながら長い夜を過ごした。
夜中にパソコンが息を吹き返す音で電気の復旧を知った。
その時間まで復旧作業に追われ続けてこれからもそれを繰り返すのであろう電力会社のみなさんのご苦労を思った。頭が下がる。
これから長い苦労が始まる。
被災者の救出、避難所の運営、ライフラインの復旧、仮設住宅の建設、瓦礫の片付け、町の再建…
阪神淡路を思い、中越地震を思って、またあの途方もなく長いプロセスが繰り返されるのかと暗澹たる気持ちになる。
が、そんなものではないということを昨夜のテレビ中継で思い知った。
阪神淡路については被災地で働いたから分かるが、あの時は活断層に沿って被害が集中して無事なところとそうでないところとが比較的はっきりとしていた。つまり、その気になれば被災地に直接アプローチ出来た。また、被害の軽い人が重い人の支援に廻ることも出来た。
でも今回は町がごっそり全部壊されている。ほとんどの人が同等の被害を受け、持てるものの全てを失っている。
だから、まったく外部からの支援を待つしかない。
被災者の救出以前に、まず安否確認だけでもまだまだ時間がかかるだろう。
さらには福島第一原発のトラブルもある。
いったい誰がどうやったらそれらの町を元に戻せるのだろうかと、そんなことを思いながらテレビの画面を見るのが辛かった。
その惨状を伝えるために撮られたヘリからの映像が、その騒音で救出作業や避難所生活にとんでもない障害と負担を与えていることを思いつつ。
いつもそうだが、いま自分に何が出来るのかと思う。
わたしはこれまでの経験で、それが、
自分の持ち場で自分に出来る経済活動をしっかり行うことだと知っている。
自分が本来抱えている責任を投げ出して、現地に赴いてボランティアに身を投じるのではないことを知っている。
しっかりと仕事をしてしっかりと収入を得て、それを支援に回せるのなら、それが一番良いことだと知っている。
明日からは計画停電がスタートする。
うちの町は初日の最初の時間帯から停電となる。そして、夕方から夜の8時までの一日2回らしい。
それがどれほどの不便だろうか?
少なくとも被災地の状況を思えば…
う~ん。
今年最初の生コン打設がようやく出来ると思っていたが、きっとプラントは操業停止に近い状態になるのだろうな。
わたしのデスクトップPCもしばらくは操業停止…かもしれない。
ブログも再びお休みとなりそうだけど、その間、誰にも恥じることのない仕事に務めたい。
こんな長々と書き連ねなければ、被災地のみなさんへの思いを表すことの出来ない自分だが、それでもまだまだ言葉が足りない気がする。
足らないあとの分は、ただひたすら、祈ろうと思う。
「ダモンネみはらし」のこと
テーマ:思い
2011/02/28 06:17
一昨日、ダモンネみはらしにおいて出村圭一さんによる津軽三味線のコンサートがありました。

生で聴く津軽三味線の澄んだ音色と力強いバチの響きに酔いしれ、途中にはみんなで民謡を歌うコーナーもあって、楽しく素敵なひと時を過ごさせていただきました。

ダモンネみはらしとの出会いは、昨年の6月、熊谷のOさんのお宅の仕事をしている時でした。
Oさん宅を施工中…たしかキッチンガーデンを作るために既存の芝をはがして別の場所に移している時のこと。
「ずいぶんと楽しそうに仕事してるねえ」
と声を掛けてくれたのがお向かいのSさんでした。
「はい。楽しいっすよ」
それからたびたび話すうちに、このSさん、いろいろ工具のことに詳しく作業内容に対する理解も早いし…
「なんかこんな仕事をなさっていたんですか?」
「いやいや、今も近所でレンガ張ってるんだよ、近所のおじさんたちと一緒に…。今度、遊びにおいでよ」
近所? レンガ張り? おじさんたち?
…なぞの言葉を残して好奇心たっぷりで話好きでファンキーなSさんは去っていったのでした。
で、昼休みにふと立ち寄ったのが「ダモンネみはらし」です。

看板には「ふるさといきいきサロン」とあり、その月の予定表が外に置いてありました。
手打ちうどん、ヨガ教室、パソコン教室、青空マーケット…
これは公共の公民館のようなところなのか…いや、それにしてはあちこちがまだ工事中だし、ガーデンなんて妙に手の掛かった手作り感いっぱいなものだし…

後々聞いて徐々に理解を深めていったダモンネみはらしについて書かせて貰いますが、間違いがあったらごめんなさい。
このダモンネみはらしは、公的な機関で福祉関係のお仕事をなさっているS家の奥さんの発案で始まりました。
地域のお年寄りが気楽に立ち寄って交流してもらえる場を作りたい。
貯蓄と退職金を使ってこのログハウスを建設し、屋根葺きなど一部は家族総出で行い、外部の舗装もご近所の方から寄贈してもらったレンガを、やはり有志が集まって敷いていったのだそうです。
さまざまな教室もすべて講師はスタッフとご近所の方でまかない、受講料も材料費代のみ。あるいは無料。
いや、お茶や菓子も出すから事実上の赤字でしょうか…
後になって市の委託事業となり補助金も出るようになりましたが、事実上のボランティア事業だとわたしは理解しています。
となれば何か手伝えることはないかと考えるのが、ガーデン工房 結 -YUI-でして、わたしも仲間に加えてもらい夏の間は月に一回ガーデニング教室を開催してダモンネの庭づくりのお手伝いをしました。

うちに在庫していたコッツ・ストーンを使ったサークルづくりにはスタッフの方のお孫さんも参加してくれました。
そうそう。
こちらのスタッフですが、館長であるSさんと現在は職場復帰中の奥さんの他、主力は奥さんの知り合いでご近所に住む3人の素敵な女性たちと、このダモンネの開設に合わせて山梨から戻ってきた(呼び戻された?)三女のYさんからになります。
こちらのガーデンは、山野草や宿根草に関する知識が豊富でなにより植物と木工をこよなく愛するYさんが、有志の方の力を借りながら育ててきたもので、そこで育てられた野草やハーブはオリジナルの野草茶になり、キッチンガーデンの野菜たちはお菓子になったして、どちらもコンサートの際には参加者全員に振る舞われることになります。
夏にはアルパという南米の小型のハープを倉品真希子さんという方が演奏して下さるオーガニック・コンサート(お礼に手作りの野菜や花を持って行って頂きました)が開催され、冬にはわたしの古い友人であるプロのフルート奏者、浜川君に来て貰って2台のフルートとピアノによるアトリエ・ソワのコンサートも開かれました。

そして、こちらは秋の青空マーケットの様子。

わたしも花と野菜とハーブの苗を安く売らせてもらいました。
忙しい仕事の合間にしかお手伝い出来ないのが残念ですが、このダモンネみはらしの、出来る人が出来ることをして、持っている人がそれぞれ持っているものを持ち寄って、手作りでみんなの心地よい空間を作ろうという取り組みは、わがガーデン工房 結 -YUI-のコンセプトととても近いものがあります。
また、植物の力を借りた園芸療法や有機野菜づくり、パーマカルチャーによる農的なくらしへの取り組みと、三女のYさんと共有するテーマも多く、勉強させてもらうことも多々あり、いろいろな方とも知り合いになって、わたしの仕事にもとても良い影響を与えてもらっている気がします。
現に一昨日のコンサートでは昨年の夏に施工させて頂いたOさんご一家も、またSさんご一家も来てくださり、秋のマーケットには小川町のYさんや、かつて大きな庭を手がけさせていただいた熊谷のYさん親子も顔を出してくださり、いろいろな交流がリンクしてさらに拡がっていくようで、すごくワクワクします。
また随時、報告させて頂きますので、お楽しみに。
よろしければ、ホームページもご覧下さい。
http://www.yui-garden.com/

生で聴く津軽三味線の澄んだ音色と力強いバチの響きに酔いしれ、途中にはみんなで民謡を歌うコーナーもあって、楽しく素敵なひと時を過ごさせていただきました。

ダモンネみはらしとの出会いは、昨年の6月、熊谷のOさんのお宅の仕事をしている時でした。
Oさん宅を施工中…たしかキッチンガーデンを作るために既存の芝をはがして別の場所に移している時のこと。
「ずいぶんと楽しそうに仕事してるねえ」
と声を掛けてくれたのがお向かいのSさんでした。
「はい。楽しいっすよ」
それからたびたび話すうちに、このSさん、いろいろ工具のことに詳しく作業内容に対する理解も早いし…
「なんかこんな仕事をなさっていたんですか?」
「いやいや、今も近所でレンガ張ってるんだよ、近所のおじさんたちと一緒に…。今度、遊びにおいでよ」
近所? レンガ張り? おじさんたち?
…なぞの言葉を残して好奇心たっぷりで話好きでファンキーなSさんは去っていったのでした。
で、昼休みにふと立ち寄ったのが「ダモンネみはらし」です。

看板には「ふるさといきいきサロン」とあり、その月の予定表が外に置いてありました。
手打ちうどん、ヨガ教室、パソコン教室、青空マーケット…
これは公共の公民館のようなところなのか…いや、それにしてはあちこちがまだ工事中だし、ガーデンなんて妙に手の掛かった手作り感いっぱいなものだし…

後々聞いて徐々に理解を深めていったダモンネみはらしについて書かせて貰いますが、間違いがあったらごめんなさい。
このダモンネみはらしは、公的な機関で福祉関係のお仕事をなさっているS家の奥さんの発案で始まりました。
地域のお年寄りが気楽に立ち寄って交流してもらえる場を作りたい。
貯蓄と退職金を使ってこのログハウスを建設し、屋根葺きなど一部は家族総出で行い、外部の舗装もご近所の方から寄贈してもらったレンガを、やはり有志が集まって敷いていったのだそうです。
さまざまな教室もすべて講師はスタッフとご近所の方でまかない、受講料も材料費代のみ。あるいは無料。
いや、お茶や菓子も出すから事実上の赤字でしょうか…
後になって市の委託事業となり補助金も出るようになりましたが、事実上のボランティア事業だとわたしは理解しています。
となれば何か手伝えることはないかと考えるのが、ガーデン工房 結 -YUI-でして、わたしも仲間に加えてもらい夏の間は月に一回ガーデニング教室を開催してダモンネの庭づくりのお手伝いをしました。

うちに在庫していたコッツ・ストーンを使ったサークルづくりにはスタッフの方のお孫さんも参加してくれました。
そうそう。
こちらのスタッフですが、館長であるSさんと現在は職場復帰中の奥さんの他、主力は奥さんの知り合いでご近所に住む3人の素敵な女性たちと、このダモンネの開設に合わせて山梨から戻ってきた(呼び戻された?)三女のYさんからになります。
こちらのガーデンは、山野草や宿根草に関する知識が豊富でなにより植物と木工をこよなく愛するYさんが、有志の方の力を借りながら育ててきたもので、そこで育てられた野草やハーブはオリジナルの野草茶になり、キッチンガーデンの野菜たちはお菓子になったして、どちらもコンサートの際には参加者全員に振る舞われることになります。
夏にはアルパという南米の小型のハープを倉品真希子さんという方が演奏して下さるオーガニック・コンサート(お礼に手作りの野菜や花を持って行って頂きました)が開催され、冬にはわたしの古い友人であるプロのフルート奏者、浜川君に来て貰って2台のフルートとピアノによるアトリエ・ソワのコンサートも開かれました。

そして、こちらは秋の青空マーケットの様子。

わたしも花と野菜とハーブの苗を安く売らせてもらいました。
忙しい仕事の合間にしかお手伝い出来ないのが残念ですが、このダモンネみはらしの、出来る人が出来ることをして、持っている人がそれぞれ持っているものを持ち寄って、手作りでみんなの心地よい空間を作ろうという取り組みは、わがガーデン工房 結 -YUI-のコンセプトととても近いものがあります。
また、植物の力を借りた園芸療法や有機野菜づくり、パーマカルチャーによる農的なくらしへの取り組みと、三女のYさんと共有するテーマも多く、勉強させてもらうことも多々あり、いろいろな方とも知り合いになって、わたしの仕事にもとても良い影響を与えてもらっている気がします。
現に一昨日のコンサートでは昨年の夏に施工させて頂いたOさんご一家も、またSさんご一家も来てくださり、秋のマーケットには小川町のYさんや、かつて大きな庭を手がけさせていただいた熊谷のYさん親子も顔を出してくださり、いろいろな交流がリンクしてさらに拡がっていくようで、すごくワクワクします。
また随時、報告させて頂きますので、お楽しみに。
よろしければ、ホームページもご覧下さい。
http://www.yui-garden.com/