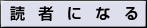田んぼの生き物調査 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト2013年 T1 仙台若林・今泉地区 6/1-2
テーマ:東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト
2013/06/12 18:20
2013年の東日本グリーン復興モニタリングプロジェクトがスタートしました。
今年は被災した田んぼの生きもの調査が6回、干潟の生きもの調査6回、島嶼のチョウ調査2回が行われ、ガーデン工房 結 -YUI-は昨年に引き続き、田んぼの調査3回に参加する予定です。
昨年は干潟調査を合せると5回の調査に参加し、そのことが少しばかり仕事を圧迫しただけでなく、他の方の参加機会まで奪ってしまったのではと反省し、控えめにしますと申込書に書き込んだら、逆にどんどん参加して下さいと研究員の方にハッパを掛けられてしまいました。
ただ、幸いなことに現時点ですでに、すべてのプロジェクトが満席となっているようです。
田んぼの生きもの調査、今年の初回は6月1日2日、仙台市若林区で行われました。

この地区は昨年の調査でも6月と8月に訪れたのですが、その時の田んぼの他に今年新たに作付を再開した田んぼも加わりました。その代わり昨年2日目に訪問した七ヶ浜の調査は中止。七里ヶ浜の皆さんは残された田んぼを除き、被災した田んぼの復旧を断念されたのだそうです。(東北大学の研究員のみなさんは引き続き、調査を継続していくとのことでした)
一年ぶりの調査に胸がときめきます。
昨年ご一緒した研究員の皆さんは勿論ですが、市民調査員の中にも旧知の方が2名おられ、再会を喜びました。昨年の緊張が嘘のよう。すでにとても居心地の良い調査環境となっていました。
初日に調査したのは、今年から作付を再開した若林区の仙台東部道路東側に位置する6枚の田んぼでした。
昨年太陽光パネル設置に関連して訪れた荒浜からすぐ近くの場所です。

午前と午後とで別の田んぼを調査したのですが、それぞれ復旧の方法が違っているという話を伺いました。
午前のそれは除塩のみ。

土が全体に黒く見えます。
これはもともとこの場所の土質なのだそうです。
そしてこちらが午後の田んぼで、表土をすっかり入替えるという手法で復旧されました。砂分を多く含んだ赤い土です。

どちらも共に、とても静かな、生きものの気配が少ない田んぼでした。少なくとも目視で確認できたのはミジンコとアメンボくらいです。
天候にも恵まれて調査開始です。

最初の、除塩だけの田んぼでわたしが捕獲できた生きものは7種。
全体では23種も見つかったそうです。
コガムシ。

バタバタ泳ぎ回るとても元気なやつでした。

その他はヒメアメンボ、エリユスリカ、ユスリカ亜科、モンユスリカ、カイミジンコ、ケンミジンコです。
なかなか地味なラインナップでしょ。
今回かなりユスリカやミジンコの見分けも出来るようになりましたが、それもこれも…
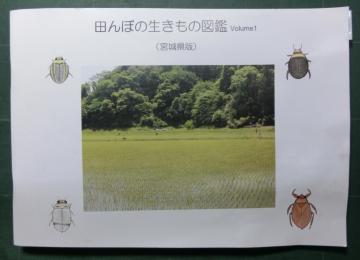
昨年、調査の都度にわれわれの意見や感想を取り入れて改訂を繰り返し、ついにいったんの完成を見た向井康夫助教による「田んぼの生きもの図鑑」です。
生きもののいる場所、動き方、身体の特徴などマクロからミクロまで丁寧にたどって、ついにその名前に行き着けるよう懇切丁寧に作られた素晴らしいガイドブックです。今年から送料込み500円で市販もするとかで、いずれこれをまとめ買いして子どもたちに配りたいと思いました。
この田んぼでは他に、

ヒメゲンゴロウ。

ザリガニの子どもとヒメゲンゴロウの幼虫。

コガムシの幼虫。
他にヤゴやニホンアカガエルなども見つかりました。
同じ種の成虫と幼虫とが同居するのはこの時期の田んぼの特徴という事ですが、それにしても今年再開されたばかりの田んぼです。生きものたちの戻ってくるスピードの速さに圧倒されました。
午後の、表土を入替えた田んぼでは、わたしは残念ながら2種。
たっぷりと集めた泥の中にヒメゲンゴロウの幼虫と、タマミジンコしか発見できませんでした。
全体ではそれでも17種。同時に調査した3枚の田んぼの、そのそれぞれの調査場所によってもかなりの差はありましたが、思いのほか多かったというのが率直なところ。
田んぼの印象からして、もっと少ないかと思っていました。

翌日は今泉地区の調査。
こちらを訪れるのはこれが3度目です。(昨年の6月の調査報告はこちらです)

過去、わたしの収穫だけに限って言うなら、午前中の対照水田(比較のために調査する、被災しなかった田んぼ)で昨年6月が5種(15種)、次の昨年8月末が13種(33種)、そして今回が13種(30種)でした。(括弧内は調査員全体の発見種数です)
稲穂が成長して生きものの生育環境が豊かに多様化する8月は、生きものの数が増えるようですが、今年の6月ですでに昨年の8月並みの種数を発見していると言うことです。(昨年8月の様子はこちらをどうぞ)
一概には言えないのですが、やはり復興から年を数えるほどに生きものが多く戻ってくると言うことでしょうか。

この午前中の対照水田で、わたしが発見した生きもの。
ヒメアメンボ、ヒラマキミズマイマイ、サカマキガイ、ヒメモノアラガイ、フタバカゲロウ、ミズダニ、ユスリカ3種、ミジンコ3種。
そして午後の復興田。

ここでも13種(30種)。これも昨年8月並みで。昨年の6月はまだ7種(18種)でした。
昨年もこの田んぼでたくさん見つけて感動したタマカイエビ。

今年もバケツの泥の表面が埋め尽くされるほどにいました。

ヒメモノアラガイ。

コガシラミズムシ。
この辺は昨年の常連ですね。

そしてザリガニ。
その他、キベリヒラタガムシ、ケシカタビロアメンボ、ガガンボなどがラインナップに加わりました。

研究者でも無いわたしの素朴な印象として、やはり時間の経過と共に生きものたちの層が豊かになっていると感じます。
初日夜の勉強会で研究員の方から報告を受けましたが、確かに生物種を移動方法によって分類すれば、まだまだ戻ってきていない種も多いのでしょう。今回発見された生きものたちの多くは水路から流れ込む水に乗ってきたもの、飛んできたもの、他の生きものに運ばれてきたものがほとんどです。
ただ、身体で感じる「生命の息吹」に限って言うなら、そこはもうすでに豊かな生きものたちの空間となっているように思えます。
そして、これからもますます豊かになっていくように感じられます。
もう少し、というかやはりあと8年かけて、その経過に立ち会いたいと思いました。
次回は6月末、石巻北上地区を訪れます。
よろしければ、ホームページもご覧下さい。
http://www.yui-garden.com/