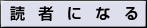田んぼの生き物調査 東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト その1 T1 東松島 6/2-3
テーマ:東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト
2012/06/15 23:02
今に始まったことではありませんが、大変ご無沙汰してしまいました。
みなさんすでにお気づきのとおり、少しばかりバタバタしておりまして、あっという間に半年がたってしまいました。
バタバタバタバタ…
いつもより少しばかり遠いところに仕事に行っていて、いつもより少しばかり完成までの時間がかかってしまって、いつもより少しばかり自宅に滞在する時間が少なかったり、休む日が無かったり、それ以外の仕事が多かったりしたというだけなのですが、その程度のことでブログさえ更新できないというのはやはり歳のせいなのでしょうねぇ。睡眠時間が5時間を切ると仕事の精度が落ちそうになるというのは、やはり情けないことです。
まあ、それはさておき…
休みは相変わらず取れないながらも、ここにきてようやく通勤時間が往復で3時間ほど浮くようになってきましたので、満を持してブログ再開です。(続く保証は無いのですが)
新しい活動も始めました。
長い表題で、本当にいつもながら恐縮ですが、
東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト。
宮城県を中心とした被災地の、生態系のモニタリングです。
島や干潟での調査もさることながら「田んぼ」調査というので思わず飛びついてしまいました。森明彦君からの知らせで、
「おもしろいボランティアの募集がありますよ」と…
彼がおもしろいという以上、それは必ずおもしろいに違いなく、ホームページで確認して、しばらく自分のスケジュールを睨みつけて、それもかなり長い間睨みつけてから、その日のうちに申し込みました。ご存じのとおりスケジュールなんて先に埋めてしまったものの勝ちなのです。
主催するアースウォッチ・ジャパンと、今回の活動内容については、それぞれのホームページをご覧いただくとして、本題に入ります。
前回の活動からすでに2週間が経過しつつありますから…
しかも明日は早朝から出発して2度目の活動に参加することになっていますから…

初回の6月2、3日の調査は東松島で行われました。
被災した、つまり津波による被害を受けて潮を被りながらも何とか除塩を経てこの春から作付を再開した田んぼと、その近くの被災しなかった田んぼのそれぞれの生物相を調査してそのデータの集積から、場当たり的ではなく生態系の回復を確認しながら自然のサイクルの中で耕作地を復興していこうとする試みです。
東北大学の生命科学研究科の皆さんがアースウォッチ・ジャパンと連携して進めてきたプロジェクトは昨年からの試行期間を経て、いよいよここから始まったのでした。
わたしもかつては高校を卒業した後の4年間を栃木県は大田原の広大な水田の中で過ごしましたので(農場で過ごした、のではなくほとんど水田の中に居たというのが正直なところ)、田んぼとは深い縁があります。
…正直、わくわくでした。

集合場所のJR仙石線高城町駅。
仙石線を仙台から石巻に向かって松島海岸を過ぎると、この駅から先が一部運航不能となっています。調査区域はそちら方面になるのでこの駅が集合地点となったのですが。
夜中の2時にクルマで出てこの駅に着いたのが8時。集合時間までにはまだたっぷり時間が有るというものの…駐車場が無い。
丸二日置かせてもらう訳だからいい加減なところに放置する訳にもいかず、かと言って解散場所もこの駅だからあまり遠くにも行けず、と悩んで駅前の酒屋さんに相談したところ、線路の反対側に月極めの駐車場があるからそちらに電話して相談してみたら!
で、相談しました。
いやあ、うちは月極めで一日貸しはしていないんだけどね…どういう事情?
…そうかぁ。それならいいよ、1台分空きがあるからさ、そこ3日でも4日でも使っていいよ。料金? そんなもん要らないよ。がんばって働いておくれ。
ぐすん。
遠藤商店さんに心から感謝です。
集合時間の9時45分。東北大学のスタッフが占部城太郎教授と指導にあたってくださる向井康夫(惜しい!)助教始め5名、一般調査員12名、アースウォッチ・ジャパンの伊藤さんの計18名が顔を揃え、大学のクルマ3台に分乗して調査地に向かいました。

ここからの調査の間、ほとんどまともに写真を撮れなかったのは、何を隠そう、その調査活動があまりに面白く、ついつい夢中になってしまったからに他なりません。

内容からして絶対に面白いだろうとは思っていましたが、そんな予想をはるかに上回る内容でした。

一日に2か所、被災した田んぼとその直近の被災をまぬかれた田んぼを訪れ、12名がその都度3枚の田んぼに分かれまず一定量の泥を採取する。次に一定時間の間、網を使って自由に(もちろんイネや畦などを痛めないように注意)水中の生物を捕獲。テントに下でトレイにあけた泥や水の中からすべての生き物をピックアップして(スポイトで、小さな網で、あるいはさじやピンセットや素手で)、スタッフからレクチャーを受けつつ分類し、そしてその種名を特定するという…
あ、そうそう。採取した泥を用水路に膝まで浸かって洗い流してくださったのは占部教授じきじきのことでありました。

とりあえず写真に収めてはみましたが、このトレイにあけた量は多すぎます。

これではちゃんと生物を特定できない。
が、わたしの場合つい欲張ってたくさん泥を集めてきたため、一定時間内に同定作業を終えるために飛ばさざるを得なかったのでした。
同じ組の女性が捕らえた…

かなり立派なカブトエビです!(すみません。こんな写真しか無くて…)
いやぁ、懐かしい。
子供の頃、無近くの田んぼでたくさん捕まえてはうまく育てられなくて死なせたものでした。
向井助教にも伺いましたが、やはり育てるのはとても難しいとのことでした。

あとはいちいち写真を撮っていませんでした。
この日わたしが捕まえてリストに載せた生き物たち…
カイエビ、タマカイエビ、イシビル、ヌカカの幼虫、ユスリカの幼虫、ガガンボの幼虫、イトミミズ、ミジンコ、ガムシ、ゴマフガムシ、チビゲンゴロウ、ミズダニ、コガシラミズムシ、アメンボ、ヒメアメンボ、ドジョウ、オタマジャクシ(ニホンアマガエル、シュレーゲルアマガエル)、モノアラガイ…

たとえば2日目の矢本地区の2つの田んぼの場合、被災した田んぼで5種類ほど、でも被災しなかった方では15種類の生き物を発見しました。
やはり、被災して除塩を終えたばかりの田んぼでは生き物の姿が少ない。
でも、それでもわたしだけでも5種類、12名全員で総合すると10種類以上の生き物が戻ってきていることが、むしろ驚きでした。被災しなかった方の生物種は全体で確かに30種を超えていましたが、その中で注目する点は被災した田んぼでは貝類が居らず、そのためにそれを捕食するヒルの仲間もいなかったことでした。貝類の成長には時間が掛る為ということでしたが、用水路などから運ばれてきたといえ、被災した方に環境の変化に敏感なカブトエビが生息していたことは驚きであり、一つの喜びでもありました。

そうしたすべてのデータをスタッフのみなさんがその場で集計して、すぐに報告して下さいました。
これはとてもありがたいことで、やはり志の高さの違いを強く感じさせられました。
慣れないわれわれに懇切丁寧な指導をしてくださり、一緒になって生き物の発見に歓声を上げてくださったスタッフの皆さんに、深い愛情と感謝の気持ちを禁じえません。
今回が初回ということで前日は心配で眠れなかったという向井助教はじめ…心から水生生物を愛してやまないスタッフのみなさんに心から敬意を表します。
そして共に調査活動に携わった初対面の調査員の面々…
こちらの方もまた、かなりの個性派がたくさん揃っていました。
生物多様性の調査は、同時に人間の生物多様性を味わう調査でもあったのでした。

本当はこうした活動の中でこれから進められていく復興について、そしてわたしたちがそれに関わっていく意味などについて、まだまだ考えたこと、お伝えしたいことははたくさん有るのですが、それはまた次回。
活動はまだまだ続きますので。
まずは明日の、2度目の活動に備えて準備を始めたいと思います。
あ、カッパも入れとかなきゃ!
みなさんすでにお気づきのとおり、少しばかりバタバタしておりまして、あっという間に半年がたってしまいました。
バタバタバタバタ…
いつもより少しばかり遠いところに仕事に行っていて、いつもより少しばかり完成までの時間がかかってしまって、いつもより少しばかり自宅に滞在する時間が少なかったり、休む日が無かったり、それ以外の仕事が多かったりしたというだけなのですが、その程度のことでブログさえ更新できないというのはやはり歳のせいなのでしょうねぇ。睡眠時間が5時間を切ると仕事の精度が落ちそうになるというのは、やはり情けないことです。
まあ、それはさておき…
休みは相変わらず取れないながらも、ここにきてようやく通勤時間が往復で3時間ほど浮くようになってきましたので、満を持してブログ再開です。(続く保証は無いのですが)
新しい活動も始めました。
長い表題で、本当にいつもながら恐縮ですが、
東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト。
宮城県を中心とした被災地の、生態系のモニタリングです。
島や干潟での調査もさることながら「田んぼ」調査というので思わず飛びついてしまいました。森明彦君からの知らせで、
「おもしろいボランティアの募集がありますよ」と…
彼がおもしろいという以上、それは必ずおもしろいに違いなく、ホームページで確認して、しばらく自分のスケジュールを睨みつけて、それもかなり長い間睨みつけてから、その日のうちに申し込みました。ご存じのとおりスケジュールなんて先に埋めてしまったものの勝ちなのです。
主催するアースウォッチ・ジャパンと、今回の活動内容については、それぞれのホームページをご覧いただくとして、本題に入ります。
前回の活動からすでに2週間が経過しつつありますから…
しかも明日は早朝から出発して2度目の活動に参加することになっていますから…

初回の6月2、3日の調査は東松島で行われました。
被災した、つまり津波による被害を受けて潮を被りながらも何とか除塩を経てこの春から作付を再開した田んぼと、その近くの被災しなかった田んぼのそれぞれの生物相を調査してそのデータの集積から、場当たり的ではなく生態系の回復を確認しながら自然のサイクルの中で耕作地を復興していこうとする試みです。
東北大学の生命科学研究科の皆さんがアースウォッチ・ジャパンと連携して進めてきたプロジェクトは昨年からの試行期間を経て、いよいよここから始まったのでした。
わたしもかつては高校を卒業した後の4年間を栃木県は大田原の広大な水田の中で過ごしましたので(農場で過ごした、のではなくほとんど水田の中に居たというのが正直なところ)、田んぼとは深い縁があります。
…正直、わくわくでした。

集合場所のJR仙石線高城町駅。
仙石線を仙台から石巻に向かって松島海岸を過ぎると、この駅から先が一部運航不能となっています。調査区域はそちら方面になるのでこの駅が集合地点となったのですが。
夜中の2時にクルマで出てこの駅に着いたのが8時。集合時間までにはまだたっぷり時間が有るというものの…駐車場が無い。
丸二日置かせてもらう訳だからいい加減なところに放置する訳にもいかず、かと言って解散場所もこの駅だからあまり遠くにも行けず、と悩んで駅前の酒屋さんに相談したところ、線路の反対側に月極めの駐車場があるからそちらに電話して相談してみたら!
で、相談しました。
いやあ、うちは月極めで一日貸しはしていないんだけどね…どういう事情?
…そうかぁ。それならいいよ、1台分空きがあるからさ、そこ3日でも4日でも使っていいよ。料金? そんなもん要らないよ。がんばって働いておくれ。
ぐすん。
遠藤商店さんに心から感謝です。
集合時間の9時45分。東北大学のスタッフが占部城太郎教授と指導にあたってくださる向井康夫(惜しい!)助教始め5名、一般調査員12名、アースウォッチ・ジャパンの伊藤さんの計18名が顔を揃え、大学のクルマ3台に分乗して調査地に向かいました。

ここからの調査の間、ほとんどまともに写真を撮れなかったのは、何を隠そう、その調査活動があまりに面白く、ついつい夢中になってしまったからに他なりません。

内容からして絶対に面白いだろうとは思っていましたが、そんな予想をはるかに上回る内容でした。

一日に2か所、被災した田んぼとその直近の被災をまぬかれた田んぼを訪れ、12名がその都度3枚の田んぼに分かれまず一定量の泥を採取する。次に一定時間の間、網を使って自由に(もちろんイネや畦などを痛めないように注意)水中の生物を捕獲。テントに下でトレイにあけた泥や水の中からすべての生き物をピックアップして(スポイトで、小さな網で、あるいはさじやピンセットや素手で)、スタッフからレクチャーを受けつつ分類し、そしてその種名を特定するという…
あ、そうそう。採取した泥を用水路に膝まで浸かって洗い流してくださったのは占部教授じきじきのことでありました。

とりあえず写真に収めてはみましたが、このトレイにあけた量は多すぎます。

これではちゃんと生物を特定できない。
が、わたしの場合つい欲張ってたくさん泥を集めてきたため、一定時間内に同定作業を終えるために飛ばさざるを得なかったのでした。
同じ組の女性が捕らえた…

かなり立派なカブトエビです!(すみません。こんな写真しか無くて…)
いやぁ、懐かしい。
子供の頃、無近くの田んぼでたくさん捕まえてはうまく育てられなくて死なせたものでした。
向井助教にも伺いましたが、やはり育てるのはとても難しいとのことでした。

あとはいちいち写真を撮っていませんでした。
この日わたしが捕まえてリストに載せた生き物たち…
カイエビ、タマカイエビ、イシビル、ヌカカの幼虫、ユスリカの幼虫、ガガンボの幼虫、イトミミズ、ミジンコ、ガムシ、ゴマフガムシ、チビゲンゴロウ、ミズダニ、コガシラミズムシ、アメンボ、ヒメアメンボ、ドジョウ、オタマジャクシ(ニホンアマガエル、シュレーゲルアマガエル)、モノアラガイ…

たとえば2日目の矢本地区の2つの田んぼの場合、被災した田んぼで5種類ほど、でも被災しなかった方では15種類の生き物を発見しました。
やはり、被災して除塩を終えたばかりの田んぼでは生き物の姿が少ない。
でも、それでもわたしだけでも5種類、12名全員で総合すると10種類以上の生き物が戻ってきていることが、むしろ驚きでした。被災しなかった方の生物種は全体で確かに30種を超えていましたが、その中で注目する点は被災した田んぼでは貝類が居らず、そのためにそれを捕食するヒルの仲間もいなかったことでした。貝類の成長には時間が掛る為ということでしたが、用水路などから運ばれてきたといえ、被災した方に環境の変化に敏感なカブトエビが生息していたことは驚きであり、一つの喜びでもありました。

そうしたすべてのデータをスタッフのみなさんがその場で集計して、すぐに報告して下さいました。
これはとてもありがたいことで、やはり志の高さの違いを強く感じさせられました。
慣れないわれわれに懇切丁寧な指導をしてくださり、一緒になって生き物の発見に歓声を上げてくださったスタッフの皆さんに、深い愛情と感謝の気持ちを禁じえません。
今回が初回ということで前日は心配で眠れなかったという向井助教はじめ…心から水生生物を愛してやまないスタッフのみなさんに心から敬意を表します。
そして共に調査活動に携わった初対面の調査員の面々…
こちらの方もまた、かなりの個性派がたくさん揃っていました。
生物多様性の調査は、同時に人間の生物多様性を味わう調査でもあったのでした。

本当はこうした活動の中でこれから進められていく復興について、そしてわたしたちがそれに関わっていく意味などについて、まだまだ考えたこと、お伝えしたいことははたくさん有るのですが、それはまた次回。
活動はまだまだ続きますので。
まずは明日の、2度目の活動に備えて準備を始めたいと思います。
あ、カッパも入れとかなきゃ!
コメント
-
矢島2012/06/22 18:21向井さん。
ご無沙汰ですが、お元気そうでなによりです(^0^)/
生態系調査とかサンプリングとか、コトバの響きは難しいけど、明らかに子供に戻って楽しんでますね!!
疲れ過ぎて帰りの道中で眠くなりませんよーに!
里山とたんぼの画像、子供時代の遊び場にそっくりで懐かしかった。
この頃は実家の田植えの手伝いにも行かないけど、久しぶりに稲刈りの手伝いにでも行こうかな、
またコメしますので更新楽しみにしてます。
矢島 -
2012/06/22 21:05矢島さま
コメントありがとうございました。
うーん。
さすが、よくお分かりですねぇ。
大学の研究グループのみなさんも一般参加の調査員の方たちも、生き物を発見するたびにキャーキャーワイワイ騒ぐ子供そのものです。そうした子供のままで大人になってしまった人たちばかりが、集まっている訳で… だから最初から和気あいあいと楽しく親しい活動ができるのでしょうね。
思えば被災地のボランティアの皆さんって、今でも残って頑張っているのはそんなタイプの方ばかりかもしれない…。復興を支えるのはきっと子供の持つ無邪気で屈託のない心なのでしょう。
お気づかい頂いたように帰りの車中は睡魔との闘いで、何度もSAで仮眠をとりました。翌日の仕事にも支障をきたすので、2回目からは奮発して新幹線を使うことにしました。
また、報告させていただきます!
これからもよろしくお願いいたします。
トラックバック
この記事のトラックバック URL :
http://blog.niwablo.jp/yui/trackback/128024
http://blog.niwablo.jp/yui/trackback/128024