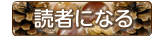三尺の雪見灯籠を据え直しながら。
テーマ:・にわしごと
2010/10/20 20:44
おとといからの現場に一区切りつけて、
屋根より高い鯉のぼり、ならぬ、トチノキのあるお宅の手入れに入りました。
モクレンやタイサンボクのように、一枚の葉が大きな樹木の手入れで、よく使う方法なのですが、
一芽に残す葉っぱの枚数をしぼって、
できるだけ十分な芽数を残しながらも、木全体は透かしたように明るくしていきました。
というのも、手入れが一年に一度の場合、芽数を極端に減らすような強い剪定をすると、その反動で、よけいに強い伸び方をするからです。
手入れの前後で、変わり映えのするように、確実に葉っぱを減らしていくわけです。
ここのお宅には三尺の(かさの直径が約90センチの)雪見灯籠がありました。
ただ、うちの会社で創った庭ではないので、詳しいいきさつまでは分かりませんが、
家の建てかえの際に、以前の庭にあった灯籠を和室の前に置いた、とのことでした。
そもそも雪見灯籠は、平たい庭石の上に、ちょこんと座っている姿が存在感あるように思います。
が、残念ながら、地べたに足をおろし、土が窪んだせいなのか、やや前傾姿勢でふんばっていました。
そこでもう一度、地ならしして、御影石を敷いて、レベルで水平をとりながら、
組み直したわけです。
ハサミを使わない手入れで庭をひきたてるのも、楽しいものです。
屋根より高い鯉のぼり、ならぬ、トチノキのあるお宅の手入れに入りました。
モクレンやタイサンボクのように、一枚の葉が大きな樹木の手入れで、よく使う方法なのですが、
一芽に残す葉っぱの枚数をしぼって、
できるだけ十分な芽数を残しながらも、木全体は透かしたように明るくしていきました。
というのも、手入れが一年に一度の場合、芽数を極端に減らすような強い剪定をすると、その反動で、よけいに強い伸び方をするからです。
手入れの前後で、変わり映えのするように、確実に葉っぱを減らしていくわけです。
ここのお宅には三尺の(かさの直径が約90センチの)雪見灯籠がありました。
ただ、うちの会社で創った庭ではないので、詳しいいきさつまでは分かりませんが、
家の建てかえの際に、以前の庭にあった灯籠を和室の前に置いた、とのことでした。
そもそも雪見灯籠は、平たい庭石の上に、ちょこんと座っている姿が存在感あるように思います。
が、残念ながら、地べたに足をおろし、土が窪んだせいなのか、やや前傾姿勢でふんばっていました。
そこでもう一度、地ならしして、御影石を敷いて、レベルで水平をとりながら、
組み直したわけです。
ハサミを使わない手入れで庭をひきたてるのも、楽しいものです。
絵を描くように、モミジの手入れをする。
テーマ:・にわしごと
2010/10/19 19:14
マツやモミジなどの剪定をして、常々思うのですが、
手入れの結果の良し悪しは、その木が大きければ大きいほど、下から見上げた時の美しさに表れるように感じます。
枝や葉の密度は、お客さんそれぞれの好みがあって、必ずしも、わしの美的感覚を押し付けることはしませんが、
「おまかせ」となると、「この木が一番きれい見えるように、ハサミを入れよう」と当然なります。
で、今日の作業のメインがモミジでした。
教科書的には、落葉の時期に剪定すること、となっていますが、一年を通して、それなりにハサミの入れ方はあるもので、
紅葉をはさむ10月、11月は庭ごとに対応が異なります。
例えば、「紅葉は少しでいいから、落ち葉が少なくなるように、葉っぱは落としておいてね」と頼まれることもあるし、
「これから紅葉するから、切るのは、夏場に焼けた葉と見苦しい徒長枝くらいにしておこう」ということもあるわけです。
どちらにしても冬場は、葉っぱがゼロ枚になるわけですから、それを見越して、
枝の流れに主眼を置きつつ、残す葉の密度や形を考えて、ハサミを入れます。
イメージ的な例えになりますが、
横山大観の落葉した雑木林の画に、点描で緑色をつけていく、ような感覚です(伝えにくいイメージですが)。
ともかく、
下から見上げた時、川の流れのような枝ぶりに、
まるで風が見えるようにさらさら葉が揺れる、
そんなモミジにしたい、と思うわけです。
手入れの結果の良し悪しは、その木が大きければ大きいほど、下から見上げた時の美しさに表れるように感じます。
枝や葉の密度は、お客さんそれぞれの好みがあって、必ずしも、わしの美的感覚を押し付けることはしませんが、
「おまかせ」となると、「この木が一番きれい見えるように、ハサミを入れよう」と当然なります。
で、今日の作業のメインがモミジでした。
教科書的には、落葉の時期に剪定すること、となっていますが、一年を通して、それなりにハサミの入れ方はあるもので、
紅葉をはさむ10月、11月は庭ごとに対応が異なります。
例えば、「紅葉は少しでいいから、落ち葉が少なくなるように、葉っぱは落としておいてね」と頼まれることもあるし、
「これから紅葉するから、切るのは、夏場に焼けた葉と見苦しい徒長枝くらいにしておこう」ということもあるわけです。
どちらにしても冬場は、葉っぱがゼロ枚になるわけですから、それを見越して、
枝の流れに主眼を置きつつ、残す葉の密度や形を考えて、ハサミを入れます。
イメージ的な例えになりますが、
横山大観の落葉した雑木林の画に、点描で緑色をつけていく、ような感覚です(伝えにくいイメージですが)。
ともかく、
下から見上げた時、川の流れのような枝ぶりに、
まるで風が見えるようにさらさら葉が揺れる、
そんなモミジにしたい、と思うわけです。
ハサミの研ぎがしっくりこないとき。
テーマ:・にわしごと
2010/10/18 20:40
高さ2.5メートルのレッドロビンが、20メートルほど続く生け垣に囲まれた庭の手入れに入りました。
約三日がかりになりそうです。
というのも、主庭のほかに、高さ約五メートルのヤマモモ、モミジを据えた玄関アプローチ、二階和室前のベランダ庭、地下部分にある吹き抜けの庭、など敷地全体に緑のあるお宅だからです。
今日は主庭の剪定が無事完了しました。
道路から3、4メートルの高さが主庭の地面、という高低差を克服するため、
いっぱいに伸ばしたアルミの二連梯子を、クレーンで吊り、命綱をつけての手入れとなりました。
大バサミで、ばしばしレッドロビンを刈り込むのですが、なぜか今日は、1センチくらいの太さの枝を切る時、刃がつるんとすべり、「食い込みが悪いなあ」という手応えが続きました。
ハサミも長い間使うと(わしの今日のハサミは2年弱くらい)だんだん研ぎで、ちびてきます。
それに応じて、刃渡りも短くなってくるようですが、わしの研ぎ方では、刃渡りをそのままにしようとして、内側が薄くなってしまうみたいです。
ともかく、研ぎが甘い、ということになります。
道具が命の商売。メンテナンスにも、まだまだ技術向上の余地あり、です。
約三日がかりになりそうです。
というのも、主庭のほかに、高さ約五メートルのヤマモモ、モミジを据えた玄関アプローチ、二階和室前のベランダ庭、地下部分にある吹き抜けの庭、など敷地全体に緑のあるお宅だからです。
今日は主庭の剪定が無事完了しました。
道路から3、4メートルの高さが主庭の地面、という高低差を克服するため、
いっぱいに伸ばしたアルミの二連梯子を、クレーンで吊り、命綱をつけての手入れとなりました。
大バサミで、ばしばしレッドロビンを刈り込むのですが、なぜか今日は、1センチくらいの太さの枝を切る時、刃がつるんとすべり、「食い込みが悪いなあ」という手応えが続きました。
ハサミも長い間使うと(わしの今日のハサミは2年弱くらい)だんだん研ぎで、ちびてきます。
それに応じて、刃渡りも短くなってくるようですが、わしの研ぎ方では、刃渡りをそのままにしようとして、内側が薄くなってしまうみたいです。
ともかく、研ぎが甘い、ということになります。
道具が命の商売。メンテナンスにも、まだまだ技術向上の余地あり、です。
スタンダードな築山に、珍しい仕立てのカリンの庭。
テーマ:・にわしごと
2010/10/16 19:00
新規のお客さんの庭の手入れに入るのは、
「どんな庭かな、今までどんな手入れをしてきたのかな。」と興味津々になるものです。
今日初めて仕事させてもらったお庭は、門冠のマツがメインの表庭と、
築山にウバメガシの段づくりを据え、築山の左右のすそ野にカリン(左)、ウメと朱モクレン(右)を配した五坪ほどの内庭があるお宅でした。
わしはせっかちMAXの親方に内庭を任せられました。
築山の内庭は、造りとしてはオーソドックスな印象でしたが、カリンの樹形が珍しいものでした。
一般的に、カリンの自然樹形は直幹ですが、ここのカリンは庭にかぶさってくるような、曲幹仕立てでした。残念ながら、この時期黄色く色づいているはずの実は一つだけでしたが。
よくよく見ると、この内庭は、和室からと居間からと90度角度の違う部屋から眺めるようになっています。
和室からは、右袖にウメを置いて築山を眺め、
居間からは築山をやや横から眺めるようになります。
カリンが直幹だとしたら、居間からはカリンの植えてある築山の左は、死角となってしまいます。が、曲幹であるおかげで、居間からもカリンの枝がしっかりと見えるのです。
庭は、いろんな角度からの目を意識して、つくるものなんだよなあ、とあらためて考えました。
「どんな庭かな、今までどんな手入れをしてきたのかな。」と興味津々になるものです。
今日初めて仕事させてもらったお庭は、門冠のマツがメインの表庭と、
築山にウバメガシの段づくりを据え、築山の左右のすそ野にカリン(左)、ウメと朱モクレン(右)を配した五坪ほどの内庭があるお宅でした。
わしはせっかちMAXの親方に内庭を任せられました。
築山の内庭は、造りとしてはオーソドックスな印象でしたが、カリンの樹形が珍しいものでした。
一般的に、カリンの自然樹形は直幹ですが、ここのカリンは庭にかぶさってくるような、曲幹仕立てでした。残念ながら、この時期黄色く色づいているはずの実は一つだけでしたが。
よくよく見ると、この内庭は、和室からと居間からと90度角度の違う部屋から眺めるようになっています。
和室からは、右袖にウメを置いて築山を眺め、
居間からは築山をやや横から眺めるようになります。
カリンが直幹だとしたら、居間からはカリンの植えてある築山の左は、死角となってしまいます。が、曲幹であるおかげで、居間からもカリンの枝がしっかりと見えるのです。
庭は、いろんな角度からの目を意識して、つくるものなんだよなあ、とあらためて考えました。
イチゴの冬越し準備、カシの木のマルチング。
テーマ:・にわしごと
2010/10/15 20:17
今日は二か所の現場で作業。
まず、午前中は昨日から入っている東西の庭。クロマツおよびゴヨウマツの手入れと掃除の仕上げです。
ニシキギやカイドウの枝から枝へメジロの家族が飛び回っているのを時折眺めながら、
のんびりとした気持ちで、でも手は休めずにゴヨウマツの古葉をむしっていました。
午後はせっかちMAXの親方とは別行動で、年一回のお客さんちでカシの生け垣剪定。
昼までとはうってかわって、スピード勝負の作業になりましたが、親方の監視の目がないほうが、手際よくできるような気がします・・・。
ところでここのカシは軒に近く、足下はインターロッキングとブロック塀に挟まれているせいか、一昨年、去年いまひとつ勢いが弱っているように見えていました。
肥料をやるにも土の部分が少なく、それでも何かしらの手を打たなければ、と
ダメもとで昨秋「バラ専用マルチングチップ」を足下に敷き詰めていました。
その効果でしょうか。今年は勢いよく伸びていました。嬉しいことに下枝も芽数が増えて、葉の色も健康そのもののになっていました。恐るべし「バラ専用マルチングチップ」。
(昨シーズンの手入れも良かったんでしょう)。
夕方、思い立って、わが家の庭のイチゴの鉢あげをしてみました。
この春、もらってきたイチゴ(実もついていた)を庭に地植えしていたものです。
梅雨の間に、その株から次々と子株が広がり、孫までできました。
あまり伸ばし続けると、一株ずつの力が弱りそうなので10株くらいになったところで、
お互いにつながっていた茎を切ってほったらかしにしていたのです。
その10株をプランターや鉢に上げて、いつ雪が降っても動かせるようにしておきます(気が早いようですが、仕事に追われるうちにすぐお正月がやって来てしまいそうで)。
来年、おいしいイチゴがどれくらいできるか、楽しみです。
まず、午前中は昨日から入っている東西の庭。クロマツおよびゴヨウマツの手入れと掃除の仕上げです。
ニシキギやカイドウの枝から枝へメジロの家族が飛び回っているのを時折眺めながら、
のんびりとした気持ちで、でも手は休めずにゴヨウマツの古葉をむしっていました。
午後はせっかちMAXの親方とは別行動で、年一回のお客さんちでカシの生け垣剪定。
昼までとはうってかわって、スピード勝負の作業になりましたが、親方の監視の目がないほうが、手際よくできるような気がします・・・。
ところでここのカシは軒に近く、足下はインターロッキングとブロック塀に挟まれているせいか、一昨年、去年いまひとつ勢いが弱っているように見えていました。
肥料をやるにも土の部分が少なく、それでも何かしらの手を打たなければ、と
ダメもとで昨秋「バラ専用マルチングチップ」を足下に敷き詰めていました。
その効果でしょうか。今年は勢いよく伸びていました。嬉しいことに下枝も芽数が増えて、葉の色も健康そのもののになっていました。恐るべし「バラ専用マルチングチップ」。
(昨シーズンの手入れも良かったんでしょう)。
夕方、思い立って、わが家の庭のイチゴの鉢あげをしてみました。
この春、もらってきたイチゴ(実もついていた)を庭に地植えしていたものです。
梅雨の間に、その株から次々と子株が広がり、孫までできました。
あまり伸ばし続けると、一株ずつの力が弱りそうなので10株くらいになったところで、
お互いにつながっていた茎を切ってほったらかしにしていたのです。
その10株をプランターや鉢に上げて、いつ雪が降っても動かせるようにしておきます(気が早いようですが、仕事に追われるうちにすぐお正月がやって来てしまいそうで)。
来年、おいしいイチゴがどれくらいできるか、楽しみです。