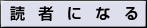パプリカが変
パプリカ、
黄色や赤になるまで待っていました。
やっと1つ黄色くなった〜 

と思ったら…

色づくのを待つことにしてから
こんな風になる事が続き…。

病気かな〜 
葉っぱで影になるからかな〜 
と思っていましたが、
今日の黄色いパプリカの状態を見て、
もしかしてナメクジ 
そうかもしれないので、急いで収穫しました 〜

今日の収穫
パプリカ

ししとう

かぐら南蛮
今年、農家の中村さんから苗をいただきました。

かぐら南蛮って、
今調べたら新潟独特のものなのですね。

私は、なすといためるのが好きです。 




インターネットで調べたら
ナメクジではないようです。
水不足
高温
が原因みたいです。
東京に 3日間行っていましたし、
コンクリートの上ですから
納得です。
おいしい スープセロリ
スープセロリは、
栽培していて
とってもお得感あります。
パスタや
トマト料理
「うーん味がいまひとつ」 というときに
スープセロリを少し入れると
「お〜 」
」
いいかんじです。

今日のスープセロリ
ただいま〜
主人が、食生活ジャーナリストの会合で
東京に行くので、車で一緒に行ってきました。
23日から25日まで留守して、
帰ってきたらオクラの花が咲いていました。
ただいま〜 。

おかえり。
なんだか犬を飼っていた頃の気持ち。
パプリカもいっぱい大きな実をつけていました。
ただいま〜

おかえりなさ〜い。
東京は、たくさんの人、人、人。
平日ということもあって、バリバリ仕事モード。
駅では、急いでいる人達にぶつからないように
歩くのが大変。
満員電車では、この気候の変化のせいか、咳をしている人が多く
帰ってきたら、私もゴホゴホ。![]()
庭ブロのみなさんのブログに癒されます。
北海道へ
ヤスヒトです。
今年の1月に
新潟大学の中野教授と、厳寒の北海道へプラントの視察に行ってきました。

この日の気温は、マイナス15度くらい。夕方だったので、気温はどんどん下がり、夜にはマイナス25度まで下がりました。そのまま足が凍りついてしまいそうな寒さで、足踏みをしていないととても立ってはいられません。
プラントのメンテナンスを行っている地元の方が、「この寒さだから、真冬には糞尿はあっという間に凍ってしまう。他の施設ではそれをボイラーで溶かして処理するが、ここは発酵熱を利用して糞尿が凍りつかないように出来る。そんな施設はここだけだよ。」と誇らしげに話して下さいました。
この牧場では250頭余りを飼育していて、
1日の糞尿はなんと12t!

発酵熱で溶かされた糞尿が固形分と水分に分けられ、固形分は堆肥舎へ運ばれます。
水分は3連の発酵塔でおよそ3日間、微生物の力で発酵処理され、もうもうと湯気を上げながら最終プールに溜まって行きます。

1頭当たり約60kgにもなる乳牛の糞尿は85%以上の水分を含みます。
通常そのままでは発酵しないため、木屑やワラ、おがくずなどで水分調整をしないと堆肥化できませんが、この施設では、そのままの糞尿から一気に処理ができます。
そのため、水分を調整する資材を追加することなく、極めて自然に近い状態で発酵処理できます。
しかも、60度以上の発酵により、草の種子や細菌類は死滅してしまい、最終プールに出てくる液肥はこの段階で匂いもかなり軽減されます。
この無希釈連続発酵技術がこの施設の特許技術です。

地元の人が「うしの糞尿の匂いは刺さる」と言うほど、プラントを通す前の匂いは強烈です。
帰りには近くの共同温泉で風呂に入ってから電車に乗りました。
新潟大学農学部へ
ヤスヒトです。 
食育の仕事柄、大学の先生と会うことが何度かあり、
そのつど発酵液の話をすると、いつもいい話をいただきました。
「面白いね。自然のものだからぜひ使ったほうがいいよ。」とか、
「そんなに少ない量でいいの!?すぐにでも、商品化したらいいんじゃない!」とか。
中には、「有機JAS取得のために有機農業へ移行する農家にとっては、3年間の移行期の土壌改良と生育のために使うといいなあ〜。学生に調べさせよう!」と言ってくださった先生もいました。
その都度、大喜びし、研究への期待をしていましたが、
その後まったく連絡もなく・・・を繰り返し、
ある時は、張り切って約束の時間に大学に行くと、いない。なんていうこともありました。
昨年の2010年は、猛暑の影響で新潟県の米の品質が過去最低を記録しました。
そんな中、「うしと花」の発酵液を使っている農家の小林さんの米が、1等米で非常に出来が良かったことがきっかけとなり、新潟IPC財団を通して研究費に新潟市の「産学連携トライアル補助金」が使える。ということになりました。

刈り取った小林さんの稲
![]()
さっそく大学で研究を引き受けていただけるかどうかを打診するためにIPC財団の百合岡さんと、新潟大学農学部大学院の中野教授を訪ねました。
中野教授は、発酵液を見ながら匂いを嗅いだり勢い良く振ったりしながら「匂いがしないね、有機物が入っているならもっと泡が出てもいいんだが・・」と興味を持っていただき、研究を引き受けていただくことが内定しました。
補助金の申請・契約の手続きは、百合岡さんと新潟市の担当の方が、とても丁寧に教えて下さいました。
こうして去年12月から、新潟大学農学部大学院での研究が始まりました。
中野教授は、農業工学が専門なので、糞尿処理プラントにも非常に興味をもってくださり、
1月には、北海道のプラントへ視察に行きました。
![]()
発酵液の分析では、通常の堆肥や液肥よりも窒素、リン、カリウムがかなり低いことがわかりました。
それにもかかわらず、生育実験では、葉の葉緑素がとても多くなることもわかりました。

このことから肥料成分の他に、植物の成長に関わるものが含まれている可能性が出てきました。