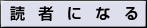窓辺のつるバラ ”アンジェラ”




これらの写真は、昨年5月15日に撮影したもの。
植付け後2年目の、我が家のリビングの出窓を彩る
つるバラ”アンジェラ”。
特にこの「アンジェラ」が好きだというわけでもなく
職業柄、奥様方に圧倒的な人気を誇るバラを自邸で
実験的に育ててみて、バラ咲く庭造りの魅力や効果と
管理のポイントを検証してみようと思ったのが
きっかけでした。
この”アンジェラ”を選んだポイントは、
以下のようなことだったと思います。
① 「四季咲き性及び返り咲き性」のもの。
つまり、一季咲きと違い長い間花を楽しめるもの。
② 色は外壁の白に際立つもので、濃いピンクを。
③ リビングの窓辺を彩るに足る枝の伸び方や樹高。
(同じCL〈つる性バラ〉に分類されるものの中でも、
家の高さほどにまで伸びるものもある。)
④ 比較的入手しやすく、栽培も容易。
そんな条件に合ったつるバラ ”アンジェラ”とは、
丸弁カップ咲きの中輪花が房咲きとなる人気種で、
街のあちこちでよく見かける。
作出は1984年kordes(ドイツ)でドイツでは
F種(フロリバンダ)に分類される。
残念なのは、
バラの大きな魅力の一つである芳香が弱いこと。
この窓辺に誘引された”アンジェラ”のここまでの
栽培のポイントを自分なりに整理・検証してみます。
一般的に、バラの栽培に適した環境とされる
「陽あたりがよく、風通しのよい場所」という面では、
なんら問題のない環境にある。
また、植付け時には、レンガで囲ったスペースの
土を少なくとも60㎝位下まで、赤玉土、ピートモス、
もみ殻くん炭などで改良した用土にすっきり入れ替え、
樹高1m位の大苗を植え付けた。
1年目からよく伸長し、
窓枠の格子に少し誘引できるほどにまで成長し、
2年目の昨年には、
旺盛な成長を見せ、花もよく咲かせた。
しかし、いくつかの問題点も発生した。
1つは、あまりに成長が旺盛で、太く勢いのよい
シュート(新しく伸びた枝)が何本も上がってきて、
誘引では収まりつかず、6・8月と2回剪定を行った。
また、四季咲きとはいえ、満開に花を咲かせるのは、
写真撮影したこの時期位で、夏場も秋もその時期を
上回るようなことはなかった。
そして2つ目は、害虫による被害。アブラムシと
チュウレンジハバチは、5月中旬から10月中旬ごろ
まで何度も発生した。
最初は、被害が拡大していくことがなかったら、
窓辺でもあるし、「できるだけ我慢してみよう」
と思ったが、窓辺ゆえ、
新芽に群がるアブラムシや
かなりの勢いで増殖しチュウレンジハバチの
無差別的な葉の食害に我慢できず
4回の薬剤散布を行った。
ガラス窓には、うっすらと薬剤の白い汚れが・・・、
サッシには落葉と害虫の糞や死骸がたまり、
管理の問題点ははっきりとしてきた・・・・・![]()
しかし、昨年の暮れ大掃除の際に窓枠から
ガラス窓を外し、
サッシの隙間までも丁寧に掃除をした。
ついでにつるバラ ”アンジェラ”の3回目の剪定と
誘引を行い、来年の健康的な成長に備え、
「ゆっくり休眠するよう」伝え、
すっかりきれいになった窓辺で新年を迎えた。

そして、2月に入りこの”アンジェラ”の今年の
健康的な成長のため寒肥を施した。
今年の肥料は、油かす・骨粉・熔成リン肥で、
土壌の物理性には特に問題ないので、
堆肥は施さなかった。
昨年もそうしたが、
生育期間中の追肥は予定していない。
( 特に必要としているようになかったから・・・)
特に必要としているようになかったから・・・)


バラに限らず、多くの植物は、
この時季の管理が結構大切。
「今年は、昨年以上にきれいな花を
いっぱい咲かせてくれよ」
「害虫や病気なんて、
自分の力で跳ね返してしまえよ!」とか、
植物たちとの対話には、
ふっと
その個体のもつ特性なんかに
気づいたりする機会がある・・・・・
今はそんな時季ではないかと思う・・・