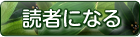昨日は、会社のパソコンのお客様打ち合わせ用ディスプレイが壊れたので、中古ショップで買ってきました。
19インチが2000円だったので、心配だったのですが、ちゃんと写りました。
また、自分専用に23インチのワイドを1万円で買いました。ホームページを作っていて2画面同時に開ける23ワイドは作業時間が短縮できます。
それにしても、今使っているソニーの15インチくらいのディスプレイは壊れないですね。本体のみ交換しながら、10年くらいは使ってますが、いまだに問題ありません。電化製品はほんとに壊れにくくなりました。
さて、よくみる厄介な樹木の病気にカナメモチのごま斑点病があります。

カナメモチ、レッドヨビン(セイヨウベニカナメモチ)で大発生すると、枯らしてしまうこともあります。
発祥した葉を直すことはできないので、これ以上広がらないようにするしかありません。
病気の葉を取り除き、落ち葉も集めて焼却します。そのあと、殺菌剤を散布するとよいです。
発生初期なら、葉を取り除けますが、全体に広がった場合は、そんなことをしたら丸坊主になってしまいます。
でも、生垣のようにたくさん植わっている場合は、1本で被害を抑えることができればいいと思います。
孤立木の場合は、すかし剪定で風とおしをよくしましょう。レッドロビンはよく伸びるので、すぐ混んででしまって病気が出やすくなります。中の枝を間引くように剪定します。
なんせ、ごま斑点病は早めの発見が大切です。
ゴマ斑点病
ムクゲにラミーカミキリ!
昨日は、会社での業務の合間にOBのお客様のカーポートの雨どいの掃除にも行きました。
雨の日に水が漏れていたので、「樋の部分が詰まっている可能性がありますよ」といって後日晴れの日に掃除に行く約束をしてました。
掃除前↓

掃除完了↓

これで、気持ちよく雨水が流れそうです。何年か経過するとカーポートの雨どいなどは詰まることがあります。特に周辺に山があると、落ち葉が飛んできやすいですね。
さて、ムクゲにきれいなカミキリムシを発見しました。ラミーカミキリムシです。
アオイ科のムクゲ属によくつく昆虫です。同じ属のハイビスカスにもつきます。
ムクゲにとっては害虫ですね。

今の時期はカミキリムシがよく庭木に飛んできます。
その幼虫はテッポウムシとも呼ばれ、幹の中に穿孔して木を弱らせる原因にもなります。
とくに、エゴノキ、モミジは注意ですが、他の木も地上から1mくらいn幹の部分に殺虫剤を塗ると効果があります(ガットサイトなど)。
成虫が、葉を食べに飛んできますので、それを捕まえるのも効果的です。
害虫は今年は多い
お庭で使われる山砂の性質
数日振りに仕事に復活できます。ご迷惑をかけました。
先週は、お客様の門扉の点検で、微調整をしてきました。

外構の扉は使っているうちに、微妙な傾きが発生します。家の玄関扉もそうなっています。そのため、微調整ができるように、柱のところに調整金具があります。不具合がありましたらすぐにご連絡ください。
さて、粘土層が広がる瀬戸市周辺で、お庭で山砂というものをよく使います。排水性がよいので、扱いやすく、価格もお手ごろです。
ただ、注意点として締まりやすく(植物にとっては悪い)、中に含まれるシルト分が不透水層を形成することがあります。
お庭の土も、森の中ではないので、メンテナンスが必要で、山砂を入れた地盤でも引き続きの改良が必要になってきます。
貸し駐車場工事
貸し駐車場を作る工事が完成しました。最大8台の車が駐車できます。
土留め工事や目隠しフェンス、造成工事、乗り入れ工事などをさせていただきました。


カムフィXの多段仕様です。プライバシーも守られます。
さて、雑草が伸びてくる季節です。お庭の草取りで苦労されている方も多いのではないでしょうか。
日本特有の気候では、勝手にどんどん草が生えて、やがて森になりますね。その場合、草抜きと草刈の対処方法があると思います。
除草剤もありますが・・・・
繰り返し草刈を行う場所では、その刈高や頻度で残る植生の種類がきまっています。毎年行う公共工事の草刈では同じような草ばかりになっています。
その多くはイネ科の草本になっていきます。繰り返しの草刈で、成長点が低いままで維持されるからです。放牧地でも繰り返し食べられることで、同じような状況になっています。
よくイネ刈の後の田んぼをみると、地面から青い葉が再び出ています。もし冬を迎えなければ、またイネが復活するでしょう。
そんな特徴がイネ科にはあります。その分取り除くのも困難といえます。
見た目の印象から、お庭の地面には芝やグランドカバーなどの単一植物でそろえたくなります。
雑草は根から抜くことが多いと思いますが、5cm程度の刈高で草刈を続ければ、イネ科の群落に変わっていきます。
遠くから見ると芝生(イネ科)と見分けがあまりつきません。
また、根を抜かない草刈は、表土が流れるのを防いだり、温度の上昇を抑えたり、生物の多様性という視点から優れているといえます。
抜いても抜いても生えてくる雑草との戦いをやめて、繰り返しの草刈でイネ科の自然豊かなビオトープ風の庭はどうでしょうか。
そんな管理の仕方も、お庭の選択枝としてあります。